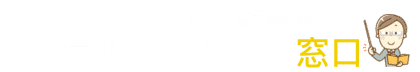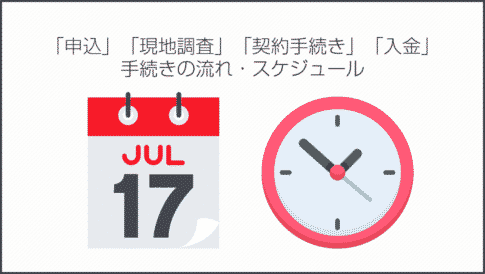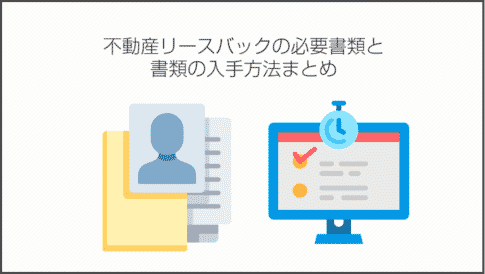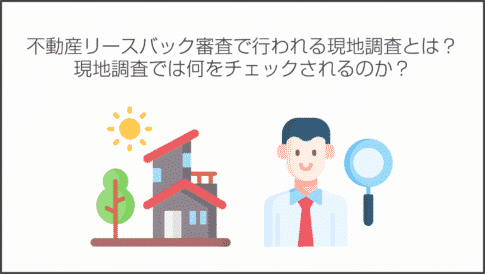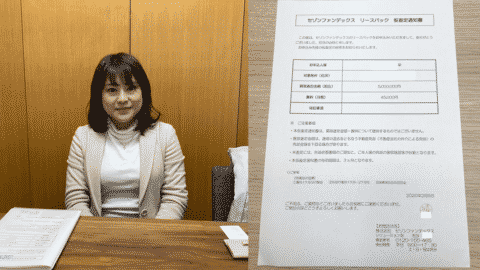リースバックとは?仕組みと特徴を整理
リースバックは、所有している自宅を売却し、その代金を現金化しながらも、そのまま同じ家に住み続けられる仕組みです。家計の立て直しや老後資金の確保など、まとまった資金が必要なときに活用されるケースが増えています。
売却と同時に賃貸借契約を結ぶため、従来の売却とは異なり引っ越しが不要です。買主となるのはリースバック会社であり、同時に貸主となります。元の所有者は売却後に借主となり、毎月の家賃を支払う形で居住を続けることができます。
リースバックの基本的な流れ
- 自宅をリースバック会社に売却する
- 売却代金を受け取り、現金化する
- 賃貸借契約を結び、家賃を支払いながら住み続ける
この仕組みによって、資金調達と住環境の維持を同時に実現できます。
特徴と活用の場面
リースバックの大きな特徴は「住み続けられる安心」と「資金調達のスピード」にあります。具体的には次のような場面で利用されます。
- 老後の生活費や医療費の確保
- 住宅ローンの返済に行き詰まったときの資金繰り改善
- 相続や離婚などで早期に資産整理をしたい場合
一方で、売却価格は市場価格より低めに設定されることが多く、加えて毎月の家賃が新たに発生するため、長期的な費用負担も考慮する必要があります。

抵当権とは?住宅ローンとの関係性
抵当権とは、住宅ローンを借りる際に金融機関が設定する担保権の一種です。債務者(借り手)が返済を滞納した場合に備えて、金融機関(債権者)が不動産を競売にかけて優先的に債権回収できる仕組みを指します。
住宅ローンを利用する多くの家庭では、購入する不動産そのものが担保として抵当権に入れられています。これは金融機関にとって貸し倒れを防ぐ安全装置であり、債務者にとってはローン利用の前提条件ともいえます。
抵当権の基本的な仕組み
- 借主は不動産を担保に入れても、そのまま住み続けることが可能
- 返済を継続する限り抵当権が実行されることはない
- 滞納が続くと、裁判所の手続きにより競売にかけられる
質権のように物を直接引き渡す必要がないため、不動産のように動かせない資産に適した仕組みとなっています。
住宅ローンとの関係性
住宅ローンは「長期かつ高額の借入」であるため、返済リスクを金融機関が負うことになります。そのリスクを軽減するために、抵当権が必ず設定されます。
具体的には、ローンを完済するまで不動産の登記簿には抵当権が記載され、返済が滞れば抵当権が行使されます。逆に言えば、ローンを全額返済することで初めて抵当権抹消の手続きが可能となり、不動産を完全に自由な状態で売却やリースバックに活用できるのです。
抵当権が及ぼす影響
- 自宅を売却する際は、抵当権を外さなければ買主が購入を避ける
- ローン残債が売却価格で完済できれば抹消可能
- 残債が売却価格を上回る「オーバーローン」では抹消が難しく、リースバックを進める障害となる
抵当権は債務者の生活や資産活用に直接関わるため、住宅ローンを組んでいる方が資金繰りに悩んだときには、まず「抵当権の状態」が大きな判断材料になります。

抵当権が残ったままの家でリースバックは可能か
リースバックを検討する際、多くの方が抱える疑問が「住宅ローンが残っている状態でも利用できるのか」という点です。結論から言うと、抵当権が付いたままでは原則としてリースバックはできません。リースバック会社は購入後に安定した賃貸運営を行う必要があり、抵当権が残っていると金融機関によって競売にかけられるリスクがあるためです。したがって、住宅ローンを完済して抵当権を抹消することが基本条件となります。
アンダーローンなら利用可能
住宅ローン残高よりも売却価格が高い「アンダーローン」の場合、売却代金で住宅ローンを全額返済できます。このケースでは抵当権を抹消できるため、スムーズにリースバックが成立します。例えば、売却価格が3,000万円で残債が2,000万円なら、売却代金から返済を済ませても1,000万円が手元に残ります。資金調達と住み続ける条件を同時に満たせる点が大きな利点です。
オーバーローンは自己資金補填や任意売却が必要
一方で、売却価格が住宅ローン残高を下回る「オーバーローン」の場合、売却代金だけでは完済できないため抵当権を外せません。このときに考えられる方法は次の二つです。
- 不足分を自己資金で補填してローンを完済する
- 金融機関と交渉して任意売却を行い、残債を分割で返済する
任意売却を選ぶ場合は、金融機関の合意が不可欠です。全ての金融機関がリースバックでの任意売却を認めるわけではなく、交渉力や取引条件次第で実現の可否が決まります。
実際の判断基準
リースバックの利用可否は、売却価格とローン残高のバランスに大きく左右されます。アンダーローンなら問題なく利用できる一方、オーバーローンでは資金調達の難しさや金融機関の対応によって可能性が制限されます。また、リースバック会社ごとに任意売却案件への対応方針は異なるため、複数社に相談して条件を比較することが望ましいです。

アンダーローンとオーバーローンの違い
住宅ローンが残った家でリースバックを検討する際、必ず確認すべきなのが「アンダーローン」と「オーバーローン」の状態です。この2つの違いを理解していないと、リースバックが可能かどうか、またその条件に大きな影響が出てしまいます。
アンダーローンとは
アンダーローンとは、売却予定の家の価格が住宅ローン残債を上回っている状態を指します。
例えば、住宅ローン残高が2,000万円で、自宅の査定額が3,000万円だった場合、売却代金でローンを完済できるだけでなく、1,000万円が手元に残ります。この場合、抵当権を問題なく抹消できるため、リースバックをスムーズに進めることができます。
アンダーローンのメリットは次の通りです。
- 売却代金でローンを完済できる
- 抵当権を抹消できるため、リースバックが成立しやすい
- 残金を生活費や老後資金に活用できる
つまり、アンダーローンはリースバックにおける理想的な状態と言えます。
オーバーローンとは
オーバーローンとは、住宅ローン残債が売却価格を上回っている状態を指します。
例えば、住宅ローン残高が2,000万円で、査定額が1,200万円の場合、売却しても800万円が不足します。この不足分を自己資金で補わなければローンを完済できないため、抵当権を抹消できず、原則としてリースバックは利用できません。
オーバーローンの問題点は次の通りです。
- 不足分を自己資金で用意する必要がある
- 自己資金を用意できなければリースバックは不可
- 不足額が大きいと利用のハードルが高い
ただし例外として、金融機関の同意を得て「任意売却」によるリースバックを進める方法もあります。任意売却では売却代金でローンを完済できなくても抵当権を外せる可能性がありますが、金融機関との交渉が必要であり、誰でも利用できるわけではありません。
判断のポイント
アンダーローンかオーバーローンかの判断は、リースバックが可能かどうかを左右する大きな分かれ目です。自宅の査定額とローン残高の比較を行い、早めに現状を把握することが重要です。特にオーバーローンの状態では、金融機関との交渉や自己資金の有無が大きなカギを握ります。

リースバックにおける抵当権抹消の流れ
リースバックを利用するためには、必ず抵当権を抹消する必要があります。抵当権は住宅ローンの返済が完了しない限り外せないため、売却代金をローン返済に充てるのが一般的な流れです。ここでは実際の手続きのステップを整理します。
売却代金で住宅ローンを完済する
リースバック契約の決済日に、リースバック会社から売却代金が支払われます。その資金を使って金融機関へ住宅ローンの残債を一括返済し、抵当権抹消の前提を整えます。残債が売却代金を超える場合は自己資金や任意売却の仕組みが必要になります。
抵当権抹消登記の実施
住宅ローンが完済されると、金融機関から抵当権抹消に必要な書類が発行されます。代表的な書類には次のものがあります。
- 抵当権解除証書
- 登記識別情報通知(または登記済権利証)
- 金融機関の委任状・資格証明書
これらをもとに、司法書士が法務局で抵当権抹消登記を行います。自分で申請することも可能ですが、リースバック取引では司法書士に依頼するのが一般的です。
手続きの同時進行
リースバック取引では、売却代金の支払い・住宅ローンの完済・抵当権抹消の手続きが同日に進められます。買主であるリースバック会社は抵当権が残っている物件をそのまま引き受けることはできないため、決済と抹消は一体的に行われます。
費用の目安
抵当権抹消登記には、登録免許税として不動産1件あたり1,000円が必要です。マンションの場合、土地と建物で2,000円程度となることが一般的です。司法書士の報酬は1万〜2.5万円ほどが相場です。

抵当権付き物件でリースバックする際の注意点
抵当権が設定された不動産でリースバックを検討する場合、一般の売却よりも複雑な条件やリスクが伴います。ローン返済が残っている状況で自宅を売却し、住み続けたいと考える方は、以下の点に注意することが重要です。
金融機関の同意が必要になるケース
抵当権を外すためには、金融機関の承諾を得ることが欠かせません。特にオーバーローンの状態では売却代金だけで残債を完済できないため、任意売却の形で進める必要があります。その場合、金融機関の判断次第でリースバックが利用できないこともあります。
リースバック会社による取り扱いの違い
すべてのリースバック会社が抵当権付き物件を受け入れているわけではありません。任意売却案件を扱える会社と、取り扱い自体を避ける会社があります。依頼先を選ぶ際は「任意売却に対応しているか」「抵当権抹消までのサポートがあるか」を必ず確認しましょう。
売却価格と残債の差額への対応
アンダーローンであれば売却代金でローンを完済し抵当権を抹消できますが、オーバーローンでは自己資金の補填が必要です。補填できない場合はリースバック自体が成立しないため、事前に収支シミュレーションを行って現実的に対応可能かを見極める必要があります。
信用情報への影響
任意売却でリースバックを行った場合、信用情報に「事故情報」として記録される可能性があります。いわゆるブラックリスト入りとなり、数年間は新たなローン契約やクレジットカードの作成が制限されるリスクがあります。将来的な資金計画に大きく影響するため、慎重な判断が求められます。
契約後の生活設計
リースバックは売却によって現金を得られる一方で、毎月の賃料支払いが新たに発生します。抵当権を外して取引を成立させても、賃料が家計を圧迫すれば根本的な解決にはなりません。売却後の家賃設定や支払能力の審査も合わせて確認することが重要です。

リースバック会社を選ぶ際のチェックポイント
リースバックを成功させるには、契約条件や資金計画だけでなく、取引を行うリースバック会社の選定が極めて重要です。会社の安定性や契約内容によって、将来的な安心感や家計の負担が大きく変わります。ここでは具体的に確認すべきポイントを整理します。
実績と資金力を確認する
リースバックは売却と賃貸の両方が一体となる取引のため、会社の経営基盤が不安定だと長期的にリスクを抱えることになります。契約件数や運営年数、上場企業グループかどうかなどを確認し、倒産リスクが低い会社を選ぶことが大切です。大手でなくても、地域密着型で長年実績がある会社なら安心感があります。
賃貸契約の種類を見極める
契約後に住み続けられる年数は、賃貸契約の形態に左右されます。
- 普通借家契約:契約更新が可能で長く住める
- 定期借家契約:更新がなく、再契約は別途交渉が必要
「できるだけ長く住みたい」のか「数年間だけで良い」のか、ライフプランに合わせて選ぶ必要があります。
買取価格と賃料のバランス
売却価格が相場より低く、賃料が高すぎると家計を圧迫します。複数社に査定を依頼して比較し、買取額と賃料の両方を総合的に判断することが重要です。特に、買取額がローン残債を完済できるかどうかが抵当権抹消にも直結します。
対応条件やエリアを確認する
リースバック会社によっては「マンションのみ対応」「首都圏のみ」など、取り扱い条件が限られていることがあります。自分の物件や地域が対象かどうかを必ず確認してください。条件が合致しない会社に相談しても時間の無駄になるため、早めに適切な会社を絞り込むことが効率的です。
担当者の対応力と透明性
金額や契約内容に納得できるかはもちろんですが、担当者が疑問点に丁寧に答えてくれるか、手続きの流れを明確に説明してくれるかも大切です。大金が動く取引だからこそ、信頼できる担当者に出会えるかどうかが安心材料になります。

抵当権がある場合にリースバックを成功させるコツ
抵当権付きの自宅でリースバックを成立させるには、単に「売却して賃貸に切り替える」だけでは十分ではありません。住宅ローン残高や金融機関との調整、リースバック会社の選定など、複数の要素を戦略的に組み合わせることが大切です。ここでは成功のための実践的なコツを解説します。
複数のリースバック会社に査定を依頼する
抵当権付き物件の場合、売却価格と残債のバランスが鍵になります。1社だけの提示条件では不利になる可能性が高いため、必ず複数社に査定を依頼して比較検討してください。
- 買取価格
- 月々の家賃
- 契約形態(普通借家契約か定期借家契約か)
を総合的に判断し、自分にとって最も現実的かつ有利な条件を選ぶことが重要です。
金融機関への相談を早めに行う
ローンが残っている場合、金融機関の同意や調整が必要になるケースがあります。特にオーバーローンの状態では、金融機関との交渉を経て任意売却扱いにしなければ進められないこともあります。支払いが厳しいと感じた時点で早めに担当窓口に相談することで、競売を避けられる可能性が高まります。
任意売却に強いリースバック会社を探す
通常の売却ではカバーできない状況でも、任意売却に対応しているリースバック会社であれば選択肢が広がります。特にオーバーローン状態で自己資金の補填が難しい場合は、「任意売却+リースバック」に対応している会社を優先的に検討すると良いでしょう。
専門家のサポートを受ける
抵当権抹消や任意売却は、司法書士や不動産会社とのやり取りが複雑になりがちです。専門知識を持つ司法書士やファイナンシャルプランナーに相談することで、手続きや資金繰りの不安を軽減できます。無料相談を提供しているリースバック会社を利用するのも有効です。